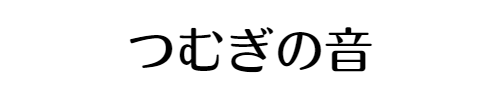有給休暇も完全に消化してついに退職日を迎えたぞー!

今までお疲れ様でした。あとは公的な手続きをしないといけないね。

公的な手続きってどこで何をするの?(面倒くさそうだな。)

OK!公的な手続きとは一体何なのかを解説していくよ!
退職日を迎え、「今日から自由だー!」と両手を広げているそこのあなた。退職後にやらなければならない重要な公的な手続きが残っています。社内での手続きは会社がやってくれたけれど、公的な手続きは転職先が決まっていない場合は自分でしなければいけません。働いている期間はそんな公的な手続きについても特に考える機会もないので、いざ退職した際にどうすればいいのか分からないこともありますよね。
この記事では、「退職後の公的な手続き」について詳しく解説していきます。特に、退職後すぐに転職をしない方・失業手当を貰う予定の方は要チェックです!
1.退職時の公的な手続きについて
公的な手続きは3つのパターンに分かれます。
・転職先は決まっているが、期間が空く人
・転職先未定、失業手当を受給予定の人
あなたはどれに当てはまりますか?それでは順番に解説していきます。
2.健康保険
健康保険とは、生活をしていて病気や怪我、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。健康保険には大きく分けて2つあります。
2.国民健康保険(国民保険)…自営業者や無職の方が加入する保険
2-1.すぐに転職する人
退職時に健康保険証を会社へ返却(直接返すor郵送)し、健康保険資格喪失証明書を発行してもらいます。「健康保険資格喪失証明書」とは「社会保険の資格を喪失したこと」を証明するためのものです。こちらを転職先に提示することによって、新しい社会保険の加入手続きを行ってくれます。
(※パートやアルバイトなどの短時間勤務を除く)
2-2.すぐに転職しない人、失業手当を受給予定の人
退職日と次の就職先の入社日が異なる月の人、退職後すぐに働かない人、失業手当を貰う予定の人は自分自身で健康保険の加入手続きをしなければなりません。手続きをしないままだと、健康保険未加入の状態ですので医療機関での窓口負担が全額自費になってしまいます。退職後は速やかに健康保険加入の手続きをしましょう。加入には3つの方法があります。
2.「任意継続保険(任継)」に加入
3.「家族の健康保険(社保・家族)」に加入
国民健康保険(国保)
国民健康保険は退職者や自営業者を対象とした健康保険です。各市町村が運営をします。離職日の翌日から14日以内に住んでいる市町村の役場(国民保険課など)へ行き手続きを行います。この期間を過ぎても手続きは可能ですが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって計算されます。手続き後、数日ほどで自宅に郵送されます。国民健康保険は、資格を喪失した日から加入することが可能なので、なるべく早めに手続きをしましょう。
・健康保険資格喪失証明書
・マイナンバーカード
・身分証明書(免許証やパスポート)
・離職票
任意継続保険(任継)
任意継続保険は、それまで勤めていた会社の健康保険に要件を満たせば最長2年まで継続して加入できる健康保険です。(※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します)保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決められ、扶養家族分の保険料はかかりません。被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担します。「保険料ってこんなにかかるのか」と今までの会社の有難みを痛感します。任意継続保険に加入する前に、国民健康保険との月額負担金額を比較しておきましょう。加入していた健康保険の種類によっては、退職後任意継続保険に切り替わっても今までの制度を受けられるメリットもあると思うので、その辺りの部分も踏まえどの健康保険に加入するのかしっかり考えましょう。任意継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に申請をしなければなりません。
・退職などにより健康保険の被保険者資格を喪失している
・資格喪失日の前日(退職日)までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」がある
・資格喪失日から「20日以内」に申請する
・健康保険資格喪失証明書
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
家族の健康保険(社保・家族)
親や配偶者など、家族が加入している健康保険の「扶養条件」を満たしている方が加入できる健康保険です。被扶養者になった場合は、保険料の負担はありません。
・自身の年収が130万円未満(失業手当・傷病手当・出産手当金などを含む)
・被保険者の家族であること
・生計維持関係にあること
・同一世帯であること(一定の条件あり)
3.雇用保険(失業保険)
雇用保険(失業保険)とは労働者の安定した雇用と雇用の促進を目的とした、国の保険制度の一つです。失業中の方以外にも、育児や介護で仕事を休んでいる方や職業訓練を受けている方へ向けた様々な給付制度があります。「一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある」という条件で雇用されていた場合、基本的に全員が加入者となり、退職後に失業手当を受け取れる場合があります。
3-1.すぐに転職する人
失業保険は、失業者が新たな就職先が見つかるまでの期間を支援し、支払われる給付金です。(※給付日数には制限があります)雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度ではありません。従って、転職先が決まっている場合は受給資格がなく手続きも不要です。
3-2.すぐに転職しない人、失業手当を受給予定の人
失業保険を受給できるのは、失業の状態にある方のみです。自分の住居地を管轄するハローワークに離職票や必要書類、証明写真や通帳などを持参のうえ、手続きをします。会社都合による退職の場合は7日間の待期期間のあとに手当てが支給されます。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加え更に2~3ヶ月間の給付制限期間を経て支給されます。
あくまでも再就職の意思があり、就職活動を行っている人に対して給付されるものです。就職をする意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは対象外となります。
・積極的に就職しようとする意志があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと
4.年金
公的年金には大きく分けて2種類あります。
1.国民年金…20歳以上の国民が全員加入する年金。
2.厚生年金…会社員や公務員が国民年金に加えて加入する年金
4-1.すぐに転職する人
退職日の翌日に新しい会社に入社する場合は、国民年金への切り替えの手続きをする必要はありません。転職先に年金手帳を提出するだけで、手続きは会社が代行してくれます。また、退職日まで期間があっても、同月内の転職、例えば「1月9日に退職、1月25日に入社」などの場合も同様です。
4-2.すぐに転職しない人、失業手当を受給予定の人
退職後すぐに転職をせず1日以上の失業期間がある場合、国民年金への切り替えが必要です。転職先が決まっていても「1月9日に退職、4月1日に入社」など退職日と入社日がひと月以上空く場合も同じことです。
国民年金への切り替え手続きの期間は、退職の翌日から14日以内です。必要なものは、年金手帳や離職票(退職日の証明ができるもの)マイナンバーカードを持参のうえ住民票がある市区町村で手続きをします。転職先が決まっていても、社会保険完備ではない場合は国民年金への切り替えが必要になります。
5.住民税
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対する税金を、今年の6月から来年5月にかけて12回に分けて支払います。
失業中の人や年収が下がった人から「住民税の支払いがきつい」という声が上がることがありますが、前年度の所得を基準にしているからです。
普通徴収…年に4回、納税者が直接納める
特別徴収…毎月の給与から天引き(会社が納付を代行)
事業主には特別徴収が義務付けられているため、会社員であれば原則として全員が給与からの天引きで住民税を納めることになります。給与明細を見て「額面はこれだけ貰っているのに手取りが少なすぎる」と思ってしまいますが、自分で納めるのと結局変わらないのだったら天引きされている方が手間が省けますよね。
5-1.すぐに転職する人
退職する会社と転職先の会社の間で、特別徴収の継続手続きを行ってもらうことで、特別徴収(給与から天引き)を継続することが可能です。退職する会社へ依頼することが難しい場合は、一時的に普通徴収に切り替えたあと、転職先の会社で特別徴収への切り替えを行いましょう。
5-2.すぐに転職しない人、失業手当を受給予定の人
退職する月により、手続きが異なります。
1月~5月に退職する場合
原則、退職する月の給与から5月分までの住民税が一括徴収されます。この時期に退職すると退職月の給与明細を見て驚きます。「手取りがやけに少ないと思ったら、住民税が一括で徴収されているではないか」と。一瞬がっかりするんですけど、5月までは自分で支払わなくて済むのでラッキーと思いましょう。ただし給与と退職金の合計が住民税の支払額を下回る場合は、普通徴収に切り替えることができます。
6月~12月に退職する場合
退職月の給与から徴収されるのはその月の住民税のみです。残りの来年5月までの分は、特に手続きをしなくても自動的に普通徴収に切り替わります。自治体から納税通知書が送られてくるので、金融機関やコンビニなどで納付すれば完了です。希望者は、退職月から翌年5月までの支払い分を一括で納めることも可能です。
6.所得税
所得税は、年初に1年の総収入を想定し、それをもとに一定の税率で毎月の給与から天引きされる、前払い方式の税金です。給与額からさまざまな控除を引いた金額(課税所得)に対して課せられます。年間所得が確定する12月に過不足を計算して返還や追加徴収をします。(=年末調整)退職の時期によっては、確定申告を自分で行う必要があります。
6-1.すぐに転職する人
年内で転職する場合は、新しい勤務先に源泉徴収票を提出すれば代わりに転職先の会社が年末調整の手続きをしてくれます。前職で貰った「源泉徴収票」「各種保険」「医療費・住宅ローンなどの控除証明書」「領収書」を大切に保管しておきましょう。
ただし11月下旬以降の入社だと、年内に手続きが終わらず年末調整に間に合わないことがあります。その場合は、自分で確定申告する必要があるため、手続きが間に合うか転職先に確認しましょう。
すぐに転職する場合も「年収が2,000万円を超える」「副業の所得が年20万円を超える」などに当てはまるときには、確定申告が必要です。
6-2.すぐに転職しない人、失業手当を受給予定の人
確定申告が必要です。基本的に2月半ばから3月半ばの間に、ご自身が居住地を管轄している税務署にて行いましょう。詳しい期間や手続き方法については、国税庁のホームページなどで確認してください。期限までに確定申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などが掛かるため、期限に注意して必ず申告しましょう。
7.まとめ
退職すると、社内・社外での手続きが多数発生します。初めての場合は特に大変だと感じるでしょうし、久々の退職でも「そういえばこんな手続きあったな」と大変だったことを思い出しますよね。確定申告なんてその時期がやって来ないとやる気が起きないものです。正直面倒くさいことばかりですが、公的なサポートを受け、税金を正しく納めるためには大切なことばかりです。一つひとつ、確実に行っていきましょう!